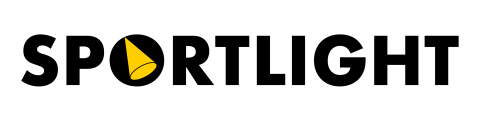正直なところ、『失われた時を求めて』は読まずに死ぬと思っていた。そんな時に一冊にまとめてしまうという煩悩の塊のような本に出会ったのである。ちょうど一日15分読書を始めようとした絶好のタイミングだ。
いざ読んでみると、意外な発見が多く面白い!なんてことはなくほぼ一月かけて嫌々読み進めるほどには重たい本であった。それでも読み終えると、『失われた時を求めて』というタイトルの意味がよくわかるし、なぜ「マドレーヌ」のくだりが色々な本で引用されるのかが理解でき、勉強にはなった。やはり多くの人に長い時代読まれていることには何かしらの理由があり、それを少しでも感じれられたのがよかった部分である。「写実的な主観」とでもいうべき思考の渦巻き(写実主義自体は物語の中でめためたにいわれているのだが)、「意識の流れ」の源流を感じる部分が要所要所にある。この「流れ」でヴァージニア・ウルフを次に読んでいきたい。(ダロウェイ婦人をかれこれ2年ぐらい積んでいる)
こういった名作を読む感覚は登山に近い。読んでいる最中は終わりが見えなく、大きな変化もない。ただ冗長な流れに疲れてくるし、放り出したくなる。しかし、読み終えた時に全てが繋がる感覚、「読んでやったぞ」という感覚は山頂から景色を眺めることと同じだ。もっとも、俺はほとんど登山したことはないのだが。有酸素運動が大嫌いだ。
訳文ではあるが心に響いた表現をいくつか抜粋。
夜の霧がバラ色と青の端布となって未だ水面を漂うなか、真珠色の夜明けの光が螺鈿のかけらみたいに散りばりはじめる。そこを何艘もの船が、帆や舳先を黄色に染めながら、斜めに射す陽に微笑みかけるように過ぎていく。夕方になって船が帰ってくるときも同じ光景が見られた。まるで人影のない幻想的な朝の光景は、ひたすら夕日を喚起させるのだった。
皿にあたるスプーンの音や、不揃いの敷石や、マドレーヌの味を、現在の瞬間において感じるとともに、遠い過去の瞬間においても感じていて、だから過去を現在に食いこませることになり、自分がいるのが、現在なのか過去なのか、すぐにはわからなくなる。ぼくの内なる存在は、その印象を有する過去と今とに共通しているもの、つまり、超時間的なもののなかでそれらを感じていることになる。そうした存在があらわれるのは、現在と過去のひとつの同一性を用いて、その存在が生きることのできる唯一の環境にいるときでしかなく、また、事物の本質を享受できる唯一の環境にいるときでしかない。
つまり、時間の外に出たときだ。