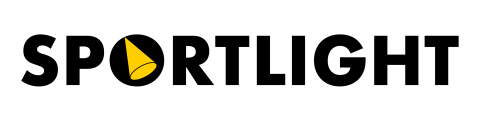仕事きっかけで読んだ南アフリカ文学。以前にも述べたようにアパルトヘイトの影響が非常に強い。
J・M・クッツェーのノーベル文学賞の受賞理由は、「数々の装いを凝らし、アウトサイダーが巻きこまれていくところを意表を突くかたちで描いた」である。ノーベル財団は「小説はよく練られた構成、含みのある対話と鮮やかな分析を特徴とする。だが同時に、彼は厳正実直な猜疑心の持ち主で、西欧文明のもつ残酷な合理主義と見せかけのモラリティを容赦なく批判した」とも評している。個人的な感想だが、『マイケル・K』よりも『夷狄を待ちながら』の方はより「西欧文明のもつ残酷な合理主義と見せかけのモラリティ」への批判色が強い。
あとがきで初めて「ローズ・マスト・フォール」運動を知った。Black Lives Matterに繋がる運動だったらしい。
あらすじ
https://amzn.to/44KA6W7
野蛮人は攻めてくるのか? 静かな辺境の町に首都から治安警察の大佐が来て凄惨な拷問が始まる。けっして来ない夷狄を待ちながら、文明の名の下の蛮行が続く。
白人→夷狄、民政官(主人公)→夷狄の少女、とヒエラルキーが物語の中に複雑に広がっている。主人公は入植者の考えに反対し夷狄に敬意を払い、彼らを守ろうとするが、夷狄の少女に対しては異常な性的行為を行う。
印象的なシーンをいくつか。帝国の考えには反対する主人公。
この世界史の秘められた一生が直ちに終わりになれば、もしこの醜い民が地表から抹消されてわれわれが誓って新たに生れ変わり、もはやなんの不正もない、もはやなんの苦痛もない帝国を運営することができるものならば、どんなにかいいことだろうに。〜しかしそれは私の取る道とはならないであろう。帝国の新たな人間とは、新たな出発、新たな一章、汚れのないページを信じるものである。
しかし、主人公は屈折した性欲を夷狄の少女に向ける。
女が着衣を脱ぐとき、私はその動作の中に、ある古い自由国家の面影を摑えることを願って女を見つめる。
夷狄の協力者と疑われ、拷問を繰り返された民政官は生存本能に従う存在に成り下がる。
私はもう一度太りたい。両手で腹をかかえるとき、満足してごろごろ鳴るほどの太鼓腹が欲しい。顎がぶよぶよに太った喉の上に沈みこみ、歩くと厚い胸板がぶるんぶるん揺れるのを実感したい。ただただ満ち足りた生活をしたい。飢餓だけは(くだらぬ望みかもしれないが)もう二度と味わいたくない。
最後、帝国が去った街で民政官は考える。
私は考えた、「人々が不当に苦しんでいるとき、それを恥辱と感じて耐えることが、その苦しみを目撃するものの宿命である」と。
日本人で戦争を経験した人が年々減っていることと同じ現象が南アフリカで起きていると思う。今の若者、特に94年以降に生まれた世代はポスト・アパルトヘイトと呼ばれているらしい。これから20年、30年と徐々に当時の記憶が薄くなっていくのだろう。日本の文化や土地に戦争の傷があるように、南アフリカの傷は隠してはいけないし、自分も一外国人として理解に努めないといけない。